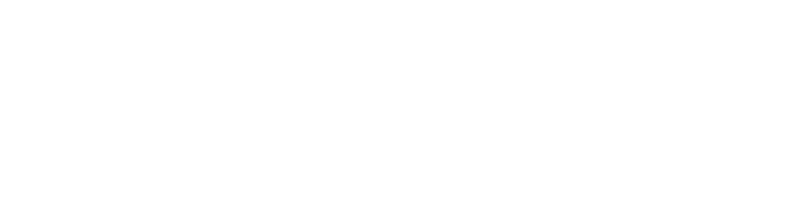あなたやご家族が「心のバランス」を崩したときに
最近、家族の様子が少し変わった──
会話が噛み合わない、急に笑ったり怒ったりする、
誰かに見られているような不安を口にする。
こうした変化に気づくと、多くの方が「どう接すればいいかわからない」と悩まれます。
また、本人も「自分が自分でなくなっていくような不安」や「周囲の視線が怖い」と感じながら、
誰にも打ち明けられないまま苦しんでしまうことがあります。
統合失調症は決して珍しい病気ではなく、誰にでも起こり得る“脳と心のバランスの乱れ”です。
そして、薬だけでなく体のエネルギー(気血水)を整えることで、
少しずつ心の安定を取り戻していくケースもあります。
統合失調症とは?
統合失調症は、脳内の神経伝達物質(特にドーパミンやセロトニン)のバランスが乱れることで起こると考えられています。
症状は大きく3つに分けられます。
- 陽性症状:幻覚、妄想、興奮、不安などが強く出る状態
- 陰性症状:感情の平坦化、意欲の低下、会話の減少など
- 認知機能の低下:判断力、集中力、記憶力の低下
治療は主に抗精神病薬が中心ですが、副作用(眠気、体重増加、意欲の低下など)が問題になることもあります。
そのため「薬だけでは整わない部分を補いたい」「体のリズムを整えたい」という方が漢方を選ばれるケースが増えています。
漢方から見た統合失調症
東洋医学では、統合失調症のような症状を「心神不安」「痰迷心竅(たんめいしんきょう)」「気逆」などと捉えます。
これは、気(エネルギー)や血(栄養)、水(体液)の流れが乱れて、心と体の調和が崩れた状態を意味します。
また、発症の背景には以下のような要因が重なっていることが多いと考えられます。
- 長期間のストレスや不安
- 睡眠不足・過労
- 栄養バランスの乱れ
- 体の冷えや血流の停滞
漢方では、これらの原因を体質ごとに見極め、
「どこから崩れたのか」を探りながら整えていくことを大切にします。
西洋薬との併用について
統合失調症の治療では、医師の診察と薬の継続が最優先です。
漢方はそれを支える「補助的な役割」として位置づけます。
実際、漢方を併用することで
- 睡眠の質が上がる
- 不安や焦りが軽減する
- 食欲や体力が回復する
といった変化を感じる方もいます。
ただし、自己判断で薬を減らすことは危険です。
医師の管理下で無理のない範囲で併用することが大切です。
最後に
統合失調症は、焦らず、長い目で向き合うことが何より大切です。
漢方は、その過程で「心と体を整えるサポート役」として寄り添う存在です。
体の声を聞きながら、無理のないペースで少しずつ。
その一歩が、きっと前に進む力になります。